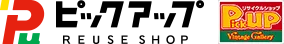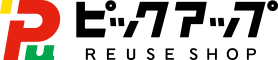記事を書いた人
自転車技士、自転車安全整備士、BAAアドバイザー
自転車歴20年 物心ついたころからリサイクルショップを愛用し、休みの日もリサイクルショップを巡る筋金入りのリサイクルショップマニア
はじめに ~筆者の経験から~
皆さんは自転車安全整備士試験をご存知でしょうか?自転車業界で働く方にとって、
自転車の安全な利用を支える重要な資格です。筆者(元フィールドギア浜松宮竹店店長)の場合、
この資格取得を目指して働きながら3年間準備し、2回目の挑戦でようやく合格しました。
この試験の受験者は自転車専門店やホームセンターに勤務されている方が多く、
軽い気持ちで初受験した際は見事に撃沈…。しかし反省を活かし徹底的に対策した結果、
再挑戦で合格できたのです。
本記事では、筆者の体験をもとに試験内容(学科・実技)と効果的な対策法、
そして準備開始から合格までの道のりを詳しく解説します。
特に 「ホイール組み(車輪組立)」 に苦戦した話や、本番の緊張対策、
初回不合格の反省点と克服法なども包み隠さず紹介します。
同じ目標を持つ皆さんの参考になれば幸いです。

自転車安全整備士とは?試験概要と受験資格
自転車安全整備士は、自転車点検・整備技術に加え、安全な利用方法の指導力も認定する資格です。
この資格を取得すると、いわゆる「TSマーク」(自転車点検整備済み証のマーク)を自転車に貼付できるようになり、自転車店では信頼の証ともなります。
整備士免許を保有していなくてもプロショップや自転車店で勤務する事は可能ですが、
試験を通して習得できる技術や知識も多い為、自転車に関わる仕事をされている方であればマストな資格かと思います。
試験は年1回程度の頻度で実施され、毎年決まった時期に行われます。
受験申込期間は毎年5月下旬~6月上旬頃で、試験自体は7月下旬~9月中旬にかけて全国各地の会場で実施されます。
私が受験したのは名古屋の会場でしたが、あまりの人の多さに圧倒された記憶があります。
定員がある会場もあり、都心近郊の人気会場は申込開始直後に満員になることもあるようです。
受験予定の方は、申込開始と同時に手続きを済ませるくらいの意気込みで準備しておきましょう。
受験資格は、基本的に18歳以上で、かつ自転車の点検整備および安全利用指導に関する実務経験が2年以上あることが条件です。
つまり、自転車店などで整備業務に携わってきた人が対象となります。
リサイクルショップでも自転車専門店やスポーツ専門店であれば受験する事が可能です。
まずは働きながら経験を積み、この要件を満たしてから挑戦しましょう。
試験科目は3部構成で、「学科試験」(筆記)・「実技試験」・「面接試験」があります。
全てに合格して初めて資格取得となります。試験の難易度は実技がやや高めで、合格率は全体で約50%前後と言われています。
学科と面接は比較的合格しやすく90%近くが受かる年もありますが、
殆どの場合、実技試験を1回で済ませられるため自転車技士試験も同時に受ける方が多いようです。
ちなみに、技士の方は学科が若干難しく、合格率で70~75%程度になるようです。
「半分は合格するから簡単?」と思うなかれ、実務経験者でも油断すると落ちることを筆者自身痛感しました。次章から、それぞれの試験内容と攻略ポイントを具体的に見ていきましょう。
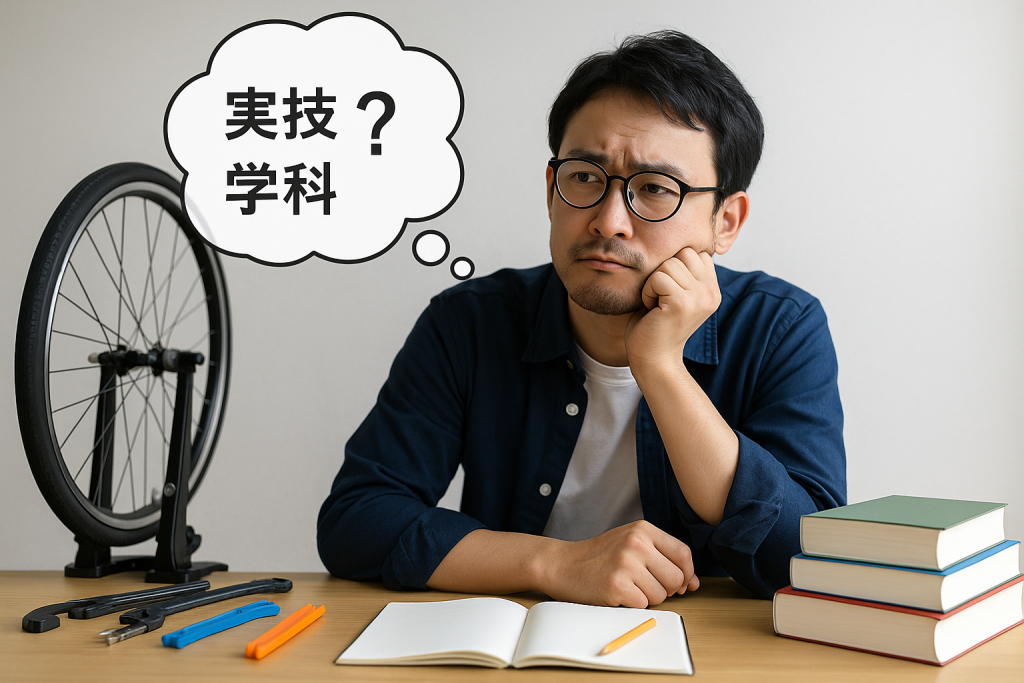
学科試験の内容と対策
学科試験では、自転車に関する幅広い知識が問われます。具体的には以下のような分野です。
- 自転車の構造・部品名に関する知識(各部の名称や役割など)
- 自転車の点検整備に関する知識(整備手順、調整方法、故障診断など)
- 自転車の安全利用に関する法規・ルールの知識(道路交通法や安全基準、マナー指導など)
出題形式は選択式が中心で、○×や複数択問題が出ます。試験範囲がとても広く、
一通り網羅する必要があります。
例えば、自転車のブレーキ種類や構造、変速機の仕組み、ライト・反射板の基準、
さらには道路交通法で定められた自転車走行ルール(車道左側通行や二人乗り禁止など)まで、
多岐にわたる知識を問われます。
対策のポイントは、まず公式・準公式の教材を活用することです。
協会が発行している「自転車組立・検査及び整備マニュアル」は整備士試験向けの基本書で、
構造や整備方法、安全指導について網羅されています。
また、過去数年分の学科試験問題集が販売されており、出題傾向や問題形式を知るのに必須です。
(令和7年度版の過去問集には直近3年分の問題と解説が収録j)過去問演習を繰り返し
出題パターンに慣れましょう。
筆者も過去問題集を繰り返し解き、初見の問題が減るように対策しました。
特に関連法規の問題は細部まで正確な理解が必要です。
単に丸暗記ではひっかけに対応できないため、なぜそのルールがあるのか背景から押さえると記憶に残ります。
例えば「普通自転車の定義」や「道路標識の種類と意味」「TSマーク付帯保険の補償内容」なども問われることがあります。
公式テキストや警察庁の交通安全サイトなどで調べ、知識を確かなものにしておきましょう。
合格基準は公表されていませんが、例年6~7割前後の得点が目安と言われます。
協会発表では1問100点満点中70点以上で合格とされています(年度によって前後しますが、
安全に関する問題で極端にミスが多い場合は総点に関わらず不合格になることも)。
満遍なく得点し、かつ法規など重要項目では落とさないことが重要です。
学科試験については、しっかり対策すれば恐れることはありません。
筆者も初回で学科は無事合格点に達しました。ちなみに一度受かれば、実技で落ちても翌年は学科が免除になります。
コツは「過去問→解説で知識補強」の反復です。
仕事で得た実践知識と法律・規定の知識をリンクさせることで、暗記ではなく理解に基づいた解答ができるようになります。
余裕があれば自転車技士(類似資格)の問題にも目を通すと、知識の幅が広がり安心です。
実技試験の内容と対策

実技試験では、新品の自転車(完成車)を一部分解した状態から組立作業を行います。
受験者は規定に沿った市販の新車を自前で持ち込み、それを「七分組み」(約7割組立済み)の状態にして試験に臨みます。
試験当日は、まずその自転車を制限時間内に分解し、指定された部位をバラします。
続いて80分以内に、完全な完成車の状態まで組み立て直しと各部調整を行います。
この一連の分解25分・組立80分の作業が実技試験の中心です。
具体的な作業内容は多岐にわたります。大まかな流れは以下の通りです。
- 分解作業(25分):ペダル、ハンドル、サドル、前後車輪などを取り外し、
後輪はホイール(リムとハブ)の分解まで行います。特に後輪のスポークは、
ドライブ側・ノンドライブ側を混ぜないよう注意しながら外します。
分解自体は慣れていれば難しくありませんが、時間内に終わらせるため手際よく進める必要があります。 - 組立作業(80分):まずホイール組み(後輪の再組立て)から取り掛かります。
ハブにスポークを通し、リムにニップルで留めていく作業です。
決められた組み方(通常はJIS組み)でスポークを編み、仮組み→振れ取り調整まで行います。
ブレーキや変速機の調整、ハンドル・サドルの取付固定、チェーン装着、
ワイヤー類の取り回し調整、タイヤ装着など、自転車を安全に走行できる状態まで組み上げます。最後にブレーキの効きや変速の全段切替、ネジの締め忘れがないかなどを確認して完了です。
実技試験の合格基準は非常に厳格です。
ただ組み立てれば良いのではなく、「安全に支障なく正しく組み上げられているか」が厳密にチェックされます。
配点上は減点方式ですが、安全性に関わる重大ミスは即不合格になります。例えば:
- ハンドルやサドルがしっかり固定されておらず、力を加えると動いてしまう
- ブレーキがきちんと調整されておらず、制動力が確保できない
- 車輪の振れが大きく、ブレーキに触れて回転が阻害される
- ワイヤーの取り付けミス(ブレーキ・シフトワイヤーが受け口から外れている 等)
- ネジの締め忘れによる部品のガタつきや脱落の恐れ
こうした安全上致命的な不備が一つでもあると減点ではなく不合格となります。
試験官は完成後の自転車を細部まで点検し、特にハンドル固定具合は強くねじって動くか確認します。ハンドルステムが少しでも動けば「容易に動くもの」と判断され不合格になり得るのです。
サドルの固定不良やブレーキの不備なども見逃されません。
受験者は組立後にこれら必須チェック項目を全て確認し、安全に問題ない状態で提出することが求められます。
ホイール組みは最大の難関

実技試験で多くの受験者を苦しめるのが、ホイール(車輪)組みの工程です。
写真はホイールを振れ取り台にセットしスポークの張りを調整している様子ですが、このスポーク組み~振れ取り作業を短時間で正確に仕上げるのは容易ではありません。
実際、不合格者の大半はホイール組みに時間を取られすぎて組立が未完成になるケースです。
協会資料によれば、車輪組立の速い人は20分ほどで完了し、多くの方でも30分前後で組み上げています。
しかし40分以上かかってしまうと時間切れで他の作業が間に合わなくなり、合格率が大きく下がるとのことです。
筆者も初受験時、このホイール組みに手間取りすぎて後半かなり焦りました…。
2回目に合格した時はホイール組自体は20分程度で完了し、振れを1mm以下にするために10分程度かけるという感じでした。
今から考えると、時間内に仕上げるのが大事なので、合格範囲内であれば精度を求めないというのも大事かなとおもいます。
ホイール組みではまず仮組み(全スポークを所定のパターンで通しニップルを軽く締める)が必要です。
15分以内で仮組みを終えるくらいのスピードが望ましいと言われます。
そこから振れ取り調整(スポークの張力を調節しリムのブレを無くす)に同じく15分程度。
理想はホイール組み全工程25~30分で終えること。この時間配分で行ければ、残りの50分弱で他の組立調整に集中できます。
ではどうやってホイール組みの速度と精度を上げるか?繰り返し練習あるのみです。
幸い筆者は店長時代、ホイール組みの機会が多少あり基礎は理解していました。
しかし試験では手順を最適化しないと時間内に終わりません。
自身は振れ取り台や工具類を簡易的なものではなくParkTool製の本格的なものにし、
普段使いなれている物で精度面をカバーするという方法を取りました。
あとは、スポークの交差手順を体に染み込ませる、振れ取りは横振れだけでなく縦振れもしっかり確認する等、コツを押さえて練習しました。また、本番に使う新品リムは繰り返し練習で歪みが生じないよう、練習用には別のホイールを用意する気配りも必要です。
YouTube等で「自転車安全整備士試験のホイール組み」動画も多数公開されているので、
それらで手順を学ぶのも有効でしょう。
筆者も先人に教わりつつ、動画を参考にJIS組みの手順を反復で練習しました。
おかげで本番では「スポークあや取りの向きが違う…」といった初歩的ミスは犯さずに済みました。

実技合格のための練習ポイント
以外と盲点になるポイントして、試験会場の作業スペースが狭い点があります。
ブルーシート約1.8m四方に収まる範囲で再現し、工具や部品はトレーにまとめて整理整頓して自転車を分解・組み立てる練習をすると効果的です。
実際の試験場でも一人あたり約1.8m×1.8m程度のスペースしか与えられません。
周囲に受験者が大勢いる中、狭いスペースで効率よく作業する訓練が必要です。
「工具を探してウロウロ…」では時間をロスするので、決まった配置で練習し、自然に手が伸びるようにしておきました。
また練習ではタイマーを使って時間管理することを強くお勧めします。
実技試験は80分という制限時間との闘いです。しかも試験本番では緊張により、普段より5分程度余計に時間がかかることもあると言われます。
筆者も本番では手が震え、思うように工具を扱えない瞬間がありました。そこで、練習では持ち時間-5~10分を目標に完了できるよう繰り返したのです。
「余裕を持って○○分短縮で組み立て完了」をクリアできると、本番でも多少のハプニングに対処できます。
特に重要チェック項目の最終確認まで含めて時間内にできるかシミュレーションしましょう。
ハンドル固定の増し締め、ブレーキの引き摺りチェック、各ナットの締付トルク確認、
リフレクター角度確認等、受験者心得(試験審査基準)に載っている事項はチェックリスト化して頭に入れておき、本番で抜け漏れがないようにします。
小さな見落としが命取りになる試験なので、最後の1分まで気を抜かず確認作業に使えるくらいのタイムマネジメントが理想です。
試験当日の心得 ~緊張に打ち勝つには~

長い準備期間を経て迎える試験当日。最大の敵は「緊張」です。
筆者は1回目の試験、本番の独特な空気に完全に呑まれてしまいました。
大勢の受験者が一斉に工具を鳴らし作業を始める中、心臓はバクバク、手は汗で滑り、頭が真っ白…。
結果、普段ならしないようなミスを連発しました。
ハンドルの締め付けトルクが緩かったりブレーキシューの位置合わせを忘れて片効きにしてしまったりといった具合です。
幸い気づいて直しましたが、その分時間ロスして焦る――悪循環でした。
ではどうすれば緊張に打ち勝てるのか?答えは残念ながら「完全に緊張しない方法」は無いと思います。
しかし、「頭で考えなくても手が動くレベルまで体に染み込ませる」ことで、多少緊張しても作業が止まらないようにすることは可能です。
スポーツや武道と同じで、体が覚えるまで反復練習した人は本番に強いのです。
メンタルトレーニングの専門家も「パニック時に考えず体が自然と動くようになるには、平時の繰り返し訓練がものをいう」と指摘しています。
筆者の場合、初回試験で痛感した弱点(ホイール組みの遅さ、焦ると手順が飛ぶ等)を踏まえ、
2回目受験までの1年間は「半自動化」をキーワードに練習しました。
具体的には、各作業工程ごとに決まった手順をルーティン化し、「手が覚えるまで」繰り返すのです。
例えば前ブレーキの調整なら、
「リムに対するシュー位置確認→ワイヤー張り調整→左右均等クリアランス確認→固定ナット本締め→
レバー握りテスト」という一連の流れを毎回同じ順序で行うよう意識しました。
何度も繰り返すうちに、考えなくても体が動くようになります。
こうなれば、本番でプレッシャーがかかっても体が勝手に正しい順序で動いてくれるのです。
緊張対策としては他にも、当日の朝に軽いストレッチや深呼吸でリラックスする、
早めに会場についてイメトレをする、といった一般的な方法も有効でしょう。
ですが何より大事なのは、圧倒的な練習量が自信と余裕を生むということです。
十分に準備した人ほど当日「いつも通りやれば大丈夫」と思えるものです。
裏を返せば、緊張で失敗したのは準備不足だった…と筆者は振り返っています。
初回不合格の反省点と合格につながった対策

最後に、筆者自身の体験を振り返りながら、合格までに得た教訓をまとめます。
初受験で不合格となったとき、原因は明白でした。
〈初回不合格時の反省点〉
- 試験の特殊性を理解していなかった
– 自転車店での実務経験だけで「何とかなるだろう」と高を括り、試験特有の手順や採点基準への対策が不十分でした。
試験ならではのポイントを把握していなかったためです。
日常業務ではまず起こらない「新品車をゼロから短時間で組立て直す」シチュエーションにもっと真剣に向き合うべきでした。 - 練習時間の不足 –
当時店の業務が忙しく、試験直前までイベント対応などに追われてほとんど練習できませんでした。
朝早くにホイール組みの練習を少しした程度で、「まあ経験あるし大丈夫かな」と甘かったのです。実技試験は経験年数よりも直前の練習量が物を言うと痛感しました。 - 時間配分ミスと焦り –
案の定ホイール組みに時間をかけすぎ、後半巻き返そうとして焦りが出ました。
焦ると普段しないミスが出て減点を積み重ねる悪循環…。計画的な時間配分と平常心の大切さを身に染みて思い知らされました。
こうした反省を踏まえ、合格を目指した再挑戦では以下のような対策強化を行いました。
〈二度目の挑戦で実践した対策〉
- 試験要項・審査基準の熟読:まず受験者心得(試験実施要領)を熟読し、求められる自転車の仕様や審査ポイントを洗い出しました。
減点項目や不合格条件をチェックリスト化し、組立て作業と照らし合わせて対策しました。
「シングルウォールのリムは避けた方がよい」など先輩受験者のブログ情報も参考に、
試験仕様に最適な車体・部品を選定しました。
安価な自転車よりシマノのコンポを使用したメーカー製クロスバイクの方が精度が出しやすく難易度が下がると考えています。 - 徹底的なホイール組み特訓:ホイール組みが鬼門だったため、毎朝出勤前にホイール組み練習を日課にしました。
仮組みから振れ取りまでの一連をタイムトライアル形式で繰り返し、最終的に25分台で完了できるようになりました。
振れ取り精度も縦横1mm未満に収める訓練を積み、本番でも車輪の振れはほぼない状態で組めるようになりました。 - 模擬試験の実施:試験1ヶ月前からは、休日に模擬試験を実施。実際の制限時間80分を測り、最初から最後まで通しで組立ててみました。
これにより弱い部分(筆者の場合後輪ハブの玉当たり調整で手間取る etc.)が浮き彫りになり、重点的に対策。
また本番さながらに作業順序を固定して練習したことで、当日は迷いなく手と体が動きました。 - 先輩からのアドバイス:幸運にも再挑戦前に資格保持者の先輩から話を聞く機会があり、コツや裏技を教わりました。
例えば「ブレーキワイヤーエンドの処理はこうすると早い」「検査員が見るポイントはここ」という具体的な助言は非常に役立ちました。
独学でも合格は可能ですが、身近に経験者がいれば積極的に頼ると良いでしょう。 - メンタル面の準備:最後の1週間は体調管理とイメージトレーニングに集中しました。
「ここまでやったのだから大丈夫」という自己暗示で平常心を保つよう努め、前夜はしっかり睡眠を取って万全のコンディションで臨みました。
こうした対策のおかげで、2回目の試験本番では大きなミスなく時間内に全工程を完了できました。
結果発表の日、合格通知を手にしたときは本当に嬉しかったです。
初回失敗したからこそ、自分の弱点を把握し対策を練れたとも言えます。
合格まで遠回りしましたが、このプロセスで得た知識・技術は自転車店での仕事にも大いに役立ちました。
おわりに ~本職でなくても整備士資格は取得できる!!~

自転車安全整備士試験は決して楽な試験ではありません。
実務経験豊富なプロでも、準備不足や慢心があれば容赦なく不合格になります。
しかし逆に言えば、正しい方向でしっかり対策すれば必ず合格できる試験でもあります。
日々の整備経験に裏打ちされた技術力に、試験特有のポイントを押さえた勉強と練習を上乗せすれば、きっと道は拓けます。
これから受験を目指す皆さんには、ぜひ計画的に準備期間を確保し、一歩一歩力を積み上げていってほしいです。
学科では公式テキストと過去問で知識を網羅し、実技ではホイール組みをはじめ弱点を重点練習しましょう。
練習では「安全第一」の観点で仕上げる習慣をつけ、本番でもミスなく完成度の高い整備ができるようにします。
緊張するのはみんな同じですが、十分な準備は緊張を和らげる最大の薬です。
筆者のように一度不合格を経験しても、決して諦める必要はありません。科目合格制度があるため、
例えば実技だけ落ちても翌年は実技に集中できます。
前回より確実に成長した自分でリベンジすれば良いのです。合格までの苦労も、資格取得の瞬間にはきっと報われます。
自転車安全整備士は、自転車利用者の安全を守る責任ある資格です。
合格への道のりで培った知識・技術・心得は、資格取得後も現場で生きてくるでしょう。
どうか自信を持って挑戦し、合格を勝ち取ってください。皆さんの健闘を心から祈っています!🚲✨
参考資料: 自転車安全整備士試験 受験案内、協会発行「実技試験ワンポイントアドバイス」、各種公式テキストおよび過去問題集も適宜参照して作成しました。